2009年11月23日
「田舎暮らし・移住」を安曇野・池田町で考える

池田町から北アルプスを望む
「田舎暮らし、付き合い方は?」をテーマに、信濃毎日新聞社主催の地域討論会「Waの会」が今日23日、北安曇郡池田町の創造館で開催され参加してきました。
池田町から望む雪を頂いた北アルプスは大変美しく感動ものでした。概して雄大な北アルプスの麓に広がる池田町をはじめとした安曇野は、美しい景観と豊かな自然環境に恵まれたところです。県内の移住希望先で1,2を争うのも肯けます。
分科会では「信州って閉鎖的?地域とどうつき合う」をテーマにトークが持たれました。
安曇野はベッドタウン化もしていて完全な田舎ではなさそうです。過疎化していないのですから行政に取って移住問題の優先順位も低い訳です。
そんな中で田舎暮らしの問題も色々と提起されました。
・果樹園に隣接した分譲地に移住してきた新住民が、消毒にクレームを付けた
・朝早くからの田んぼのししおどしの音やカエルの音がうるさいので何とかならないか
・自分のことは自分でするからと自治会には入らない新住民が半数を超えた etc
一般的には新しく入ってきた人が、「郷に入っては郷に従え」の例え通りで、「入れていただく」の謙虚な気持ちでその土地にとけ込む努力が必要でしょうし、受け入れる方でも広い心でそれを受け止める寛大な気持ちが必要なのだと思います。
例外はあるとは思いますが、私の今まで見聞きした経験では一般的に「過疎化が進んだ地域ほど移住者に優しい」ということが言える気がします。
それと私にとってはこの会場で私のブログを見て連絡をくれた、善光寺門前で空きや問題の解決に取り組む信州大学工学部の現役の学生さんに初めてお会いできたのは嬉しい出来事でした。まさに「よそ者・馬鹿者・若者が地域を変える」を地で行っている感じで期待が持てました。
2009年01月17日
「東京発信州行き鈍“考”列車30年」(扇田孝之著)を読む

「東京発信州行き鈍“考”列車30年」 扇田孝之著・現代書館刊 定価1800円・税別
現東京都副知事の猪瀬直樹氏が好んで使う、「時速4キロと時速50キロの文化」という概念の提唱者が、大町市在住の地域社会研究家であるこの本の著者扇田孝之氏です。
著者は若き法哲学の学究生として毎夏長野県の学生村で過ごすうち、信州がすっかり気に入ってしまい、ついには今から30年前、自ら大町市郊外簗場(やなば)の山荘経営者として、東京から移住してしまった経歴をお持ちです。当時はほとんどの住宅に冷房装置がなく、長野県内には都会の暑い夏を避けて勉強するための学生村や学者村が、数多く誕生していたのです。
当時の移動は徒歩(時速4キロの文化)と公共交通機関の時代、その後の高度経済成長の伸展と共に到来した車社会(時速50キロの文化)への劇的な変遷は、著者が移住した信州の片田舎にも大きな変化がもたらされました。
その中にあって著者はそれを非常に冷静な目で見つめます。と同時にその目と行動は、単なる信州の山荘オヤジの域を超えて、白馬国際映画祭のプロデュースなど全国・世界へと幅広く展開されました。
大変広い視野と、昨日今日ではない長い実体験が相まっての都会暮らしと田舎暮らしへの洞察など、その指摘には大いに納得させられます。そして今将に未曾有の世界的大不況の到来という先の見えない閉塞感の中にあって、私たちの持つ従来の都会と田舎に対する価値観も根底から覆るかもしれない状況に、著者が示す多くの示唆は大変有用に感じました。
またあれから30年を経て、バブルの頃の喧騒も嘘のように田舎から去った今日、著者夫妻の落ち着いた日々の暮らしの中で感じ取れる、身の回りで起きる微妙で繊細な四季や自然の変化に対する細やかな描写のなかに、著者の愛する信州に寄せる熱い思いを感じることも出来ました。
さらに私が思うに、特に著者は随筆家として大変な美文家で、無駄・無理のない流れるような文章と豊かな表現力にも大いに感心させられました。是非ご一読をお勧めいたします。
2008年11月30日
不景気と田舎暮らし希望者の関係は?

今日11月30日(日)11:00~16:00まで東京有楽町駅前の東京国際フォーラムで、長野県及び県内の松本市、駒ヶ根市、中野市、飯山市、原村、 木曽町、信州新町が参加して「信州の田舎暮らしセミナー・相談会」が行われました。今年も私はオブザーバー・お手伝いで参加してきました。
メディアが団塊の世代の定年移住問題としてこぞって取り上げた一昨年・昨年とは変わって、今年はいたって落ち着いた雰囲気の中、さらにここに来てアメリカ発100年に一度といわれる程の世界的・急激な不景気で、長野県・信州への移住希望者の動向が気になっておりました。
いざふたを開けてみると、参加者の数は昨年並みだった感じです(200名位か)。
そして私が聞いた相談者の話から類推するに、今回参加した方々は数年前から考えたり準備をしてきた方が多く、直接今の不景気には影響を受けていない様でした。
ただ「将来的には漠然とした不安を感じるので、信州で‘地に足の着いた人間的な暮らし’がしたい」とか、コンピュータ開発で自営の30代男性は「仕事の70%が金融関係で、来年はかなり厳しそうなので一層転身・移住の思いは強くなっている」、「古民家に住みたいが貴重な蓄えを無駄には出来ないので、最初は現地の賃家にしばらく住んでみてじっくり決めたい」などという声が有りました。また何らかの形で農業に携わりたいという希望が20代から60代まで幅広く聞かれ、今現実の物となりつつある未曾有の先行き不安の中で、将来を模索する真剣な相談者の思いを感じました。
さらに私の総括的な感想としては、この急激な不景気で実は今、大半の人はこの先の動向を見極めるためにじっと様子見の状態で、その影響が「信州・長野県への移住・交流」に本格的に及ぶのは来年以降、そしてそれはこれから顕在化すると思われるリストラや倒産・廃業で都会暮らしを止めて地方へ移住しようとする人が増える(その中には地方で農業に携わりながら、自給自足的な生活を希求する人が多く含まれると思われます)一方、不景気で出来るだけ動かずに出費を抑えようと考える人(都会から動かない人)も増えるという、二つの相反する動きが出るような気がします。
また今年参加してみて、移住に当たって具体的な物件情報を求める相談者が多いので、次回は不動産関係の代表の参加が有ると、相談者の便宜にさらに良く答えられるのではと思いました。
追記
不景気が進行すると地方の就職先が減って、地方を捨てて都会へ出る人も増えるという事態も考えられます。ただ今将に進行している事態は、以前のように中国などに日本国内の、主に地方が担っていた単純加工の生産が移ってしまう事から起きる不景気ではなく、アメリカの購買力が激減したことが起因しているので、輸出で潤っていた名古屋を中心とする東海地方や、金融などアメリカから還流される外資の流入が大きかった東京すら例外ではないので、都会に行けば職に有り付けるとは必ずしも行かないのではないでしょうか。
長野県はエプソンなど一部の例外を除いてガリバー型の大企業は余り無く、精密・電子・機械・食品など様々な職種の中小企業が大変集積した地域です。余り知られていませんが優れた技術を持つベンチャー型の企業も多いです。ですから親亀が転けたら皆転けたと言うことはなく、その代わり小さな倒産や廃業などの浮沈は頻繁ですが、贅沢を言わなければ就職先は何とかなるのではないかと思います。甘いかな?
2008年09月24日
佐久クラインガルテン望月、10月3日から募集開始

長野県の東部に位置する、佐久市が旧望月町地区で造成中の、滞在型市民農園「佐久クラインガルテン望月」の第一期募集受付が、いよいよ10月3日から11月21日まで行われます。
今回の募集は、バリヤフリータイプ1区画を含む全20区画、全て電気・ガス・上下水道・電話・インターネット使用可能の簡易宿泊施設(ラウベ)付、年間使用料38万円となっています。また募集は県外者優先ですが、ここに住所を移すことは出来ません。
周りには温泉や多くのゴルフ場、名所旧跡や癒しの森などがあり、積雪も長野県内としては少なく、通年で楽しめるところだと思います。
県内で先行して開設されている松本市の旧四賀・奈川地区のクラインガルテンも、毎年約10倍の抽選倍率と聞きますが、ここは首都圏からも近く同様になると予想されます。
詳しくは、
佐久市役所 経済部 耕地林務課 農村整備係 TEL: 0267-62-2111 内線:471
HP http://www.city.saku.nagano.jp/sangyo/kleingarten/index.html
2008年07月08日
田舎暮らしと都会暮らし、どちらがエコか?

7月7日七夕、長野市内にて

7月7日、長野市温暖化対策市民公開講座(於・信州大学工学部)
報道によると現在開催中の洞爺湖サミットで、2050年までに温室効果ガスの排出量を半減させることを、世界全体の目標として採用することを主要国が求めていくことで一致したようです。なんだか良く分かりません。地球温暖化の防止は大変困難だと言うことでしょうか。
さて私は時を同じくして長野市で開催された温暖化対策市民公開講座を聴講していて、半分夢見心地で思い浮かんだことがあったので、はっと我に返ってメモしました。日頃「田舎暮らし」を勧めている者にとっては大変気になるところです。
田舎暮らしと都会暮らし、どちらがエコか? その判定に関するポイントを挙げると
田舎暮らしの
功
クーラーの使用率が低い(自然空調)
深夜活動が少ない
緑が多い(二酸化炭素の吸収率が高い)
地元の食材使用が多くフードマイレージ少ない
人口が少ないので二酸化炭素の総排出量少ない
罪
車依存度が高い(公共交通機関が発達していない)
断熱効率の低い住宅・ビルが多い(古い建物が多い)
一人あたりの二酸化炭素の排出量多い
都会暮らしの
功
公共交通機関が発達している
効率的な空調システム・断熱効率の高いビル、マンションが多い
一人あたりの二酸化炭素の排出量少ない
罪
慢性的な交通渋滞
深夜活動が盛ん(繁華街は不夜城)
人工的な空調に頼る(高エネルギー消費型事業所・工場)
緑が少ない
地元の食材使用が少なくフードマイレージ高い
人口が多いので二酸化炭素の総排出量多い
2008年04月21日
第二の人生は信州・小布施で!都会人の情熱に地元宅建業者が感銘

栗菓子店や造り酒屋が軒を連ねる信州・小布施町のメインストリート

信州・小布施と言ったら、なんと言っても葛飾北斎(写真は北斎館正面)
長野県の北部に位置する県都長野市の北東部に、千曲川を隔てて隣接する小布施町は、面積は大変小さな町ですが、今や全国でも有名な、何でこんな処にこんなに多いのかと誰もが驚く栗菓子店や造り酒屋をはじめとした歴史を感じさせる商店街の町並みと、りんごなどの果樹を中心とした田園風景とのバランスが絶妙で、住民が自ら力を合わせて地域起こしを行った結果が実った大変魅力に溢れた町です。
県外からの移住希望も多いと聞きますが、優良農地が多い事や住民の地元への愛着心が強いので、宅地や中古住宅物件は薄いそうです。
そんな中で60歳代の東京に住む都市住民が、「第二の人生は是非信州・小布施に住みたい」とその夢の実現に情熱を燃やし、地元宅建業者さんがそれに感銘してお手伝いすることで、一歩を踏み出したという例を聞きました。
ミニ開発を許さない町当局の意向もあり、平均100坪前後と大きい面積の地元向けの宅地分譲地だったそうですが、ネットで以前から継続的に長野市近辺の不動産情報をウォッチしていたその方の目に留まり、現地を早速見学。北信五岳が正面に望めるそのロケーションにもぞっこんで、地元宅建業者さんに自分の思いの丈を熱く語ったそうです。そして地元向けと決めていたその業者さんも最初はびっくりしたそうですが、最後には根負けし見事契約と相成ったとの事。
今までは県外からの移住者のことを全く想定していない地元不動産・宅建業者さん、これからは大いにあり得る話ですよ。
(株)長野ジャシイHP
http://www.naganojassi.co.jp/
2008年01月23日
田舎暮らし情報誌3点セットプラス1 その3
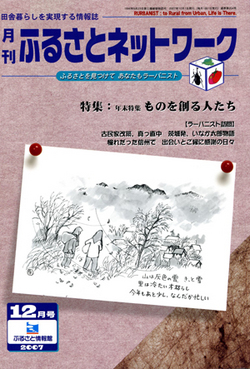
田舎暮らしを実現する会員制月刊情報誌「ふるさとネットワーク」 ふるさと情報館刊
都市と農村を結び「都市生活者の田舎暮らし実現を支援」するとともに、「農村地域の活性化」を目的として様々な事業を展開しているのが、東京四谷に本部を置く「ふるさと情報館」です。
ここが発行するこの会員制の情報誌は、田舎暮らしの手引き書として新しいライフスタイルとしての田園生活の提案をしていますが、なんと言ってもその特長は豊富な物件情報と、体験情報でしょう。それもそのはず、ここ自らが宅建免許を持っていて、全国の豊富な不動産物件情報を提供して、掲載物件の現地案内、売買契約、物件の引き渡し、所有権移転登記に至るまで不動産仲介業務を行っています。実績は既に3000世帯を超えるそうです。
かつて20年に亘って農村雑誌「家の光」の編集に携わった経験を持つ代表の佐藤彰啓さんは、その経験を基に都会と地方との交流や地域起こしの観点から記された、今や田舎暮らしのバイブルとも言える「田舎暮らし虎の巻」の著者でもあり、自ら山梨県八ヶ岳山麓に田舎暮らしの疑似体験ができる宿泊施設「田舎暮らし体験館」も運営して、田舎暮らし希望者の実践指導も行っています。
「ふるさと情報館」
http://www.furusato-net.co.jp/
2007年12月21日
田舎暮らし情報誌3点セットプラス1 その2

会員制季刊誌「100万人のふるさと」 認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
連合・JA・経団連・生協・様々な団体・個人・地方自治体などが母体の認定NPO法人で、作家の立松和平さんが理事長です。東京の銀座で「ふるさと暮らし情報センター」を運営して、ふるさと回帰に関する全国の自治体のパンフレットや資料を常備し、田舎暮らしを希望する方に具体的な地方の情報を提供すると共に、各種相談に応じています。ふるさと暮らしに関するセミナーも随時開催。また毎年秋には東京と今年からは大阪でも大規模に「ふるさと回帰フェア」のイベントを開催しています。(この模様は、このブログの10月7,8日を参照下さい)
このNPO法人の特徴は、田舎暮らし関連の全国組織のNPO法人として最大で、その中でも数少ない「認定NPO法人」(寄付金に優遇税制が適用される)であること、また全国の多くの自治体と連携していますが、あくまで主体は純粋な民間として運営されていることです。最近はマスコミの取材も多く、今や全国の「田舎暮らし」関係を代表する民間団体となっていると言っていいと思います。去る10月10日には、移住支援に大変積極的なあの東国原宮崎県知事が、宮崎県のブースも有るこの法人の銀座のセンターを訪問し、大騒ぎだったようです。なお我が長野県関係では、飯山市・松本市のブースが設置されています。
認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
http://www.furusatokaiki.net/
2007年12月20日
田舎暮らし情報誌3点セットプラス1 その1

1,月刊田舎暮らしの本
先日、「これから田舎暮らしのビジネスに本格的に取り組みたい」という長野県内の建設関係の方から、問い合わせを頂きました。近々私を訪ねてくるようです。要は「何をしたら商売になるか」と言うことを聞きたいのだと思います。私はまだまだ微力だし、どれほど力になれるかわかりませんが、「信州が多彩な人材によってより活性化され、更に魅力あふれるふるさとになるために力を尽くしたい」という気持ちがお有りならば、お会いしたいと思います。
ところで多少それに関連するかもしれませんが、全国的に田舎暮らしの移住や体験を考えている人が、大概見ていると思われる情報誌(3点セットプラス1)を紹介しましょう。「田舎暮らしビジネス」に携わる人も必見なのです。もう見ているよという方ごめんなさい。
1番目は宝島社から出ている、「月刊田舎暮らしの本」です(上記)。1987年の創刊を誇る老舗の情報誌です。また唯一の書店で買える、全国版田舎暮らし情報専門の月刊誌でもあります。最近リニューアルされて680円(税込)という更にお手頃な価格になりました。豊富な体験談と物件情報が掲載されている他、さすが日本の田舎暮らしの情報誌をリードしてきた老舗だけ有って、田舎暮らしライターの一線級の執筆陣が揃っています。長野市郊外飯綱高原在住のエッセイスト、日乃詩歩子(ひの・しほこ)さん(「田舎暮らしはもう大変」「ポール・スミザーのナチュラル・ガーデン」の著者)も時折執筆されています。
「月刊田舎暮らしの本」
http://tkj.jp/mag/mag_002.html
2007年10月08日
池田理代子氏「ふるさと回帰フェア」で田舎を大いに叱る!?

順番は前後しますが、5日夕方から同じく大手町の日経ホールにて、
「ふるさと回帰フェア」の前夜祭として開催されたシンポジウムで、
「ベルサイユのばら」の作者として有名な漫画家で、
最近では声楽家としても精力的な活動をされている池田理代子さんが、
パネラーとして参加されたパネルディスカッションを聞きました。
池田さんは東京と八ヶ岳山麓別荘(すみません、長野県かは確認しておりません)
のいわゆる二地域居住実践者で、
さぞかし田舎暮らしの良さをアピールされるのかと思っていましたら、
冒頭からその予想は見事に裏切られました。
「田舎は純朴と思っていたけれどそうではない」、
最初は何のことかと思いました。その真相とは。
池田さんは別荘を空ける間、地元の人に管理をお願いしていたそうです。
ある日その別荘に戻ってみると、部屋が荒らされていた。
それでよく調べてもらうと、びっくりした事がわかった。
管理を任されていた人が、自分も外出したり留守する時に、
知り合いの主婦に管理の仕事を孫請けに出していた。
その主婦が事もあろうに、携帯出会い系サイトで知り合った後の出会いを、
池田さんの別荘でしていたらしい。
「こんな所まで」と池田さんの怒ること、聴衆も冒頭から予想も出来ないことで、
戸惑っていたとおもいます。
田舎と言えども現代の悪しき風潮からは、免れることは出来ないのでしょう。
ただ私はその時思ったのです。
「例え田舎といえども完全な理想郷はあり得ない」。
例を出して誠に恐縮ですが、長野県と似た状況にある東北のある県は、
全国でも人口当たりの犯罪率の低さが、日本で1,2の安全な所、
またおいしい米どころ、おいしい魚の豊富な豊かな県です。
ところがその中でも正に日本の田舎の典型のようなところで、
何でというような悲惨な幼児連続殺害事件も起きました。
また自殺率が全国1位、出生率全国最下位、自然増加率全国最下位、
婚姻率全国最下位、これは何を物語るのでしょうか。
断言は出来ませんが、濃密で変化の少ない人間関係、
これは一方で波風の少ない穏やかな生活空間をもたらしますが、
それは一方で昔からのしがらみに縛られた窮屈な空間とも言え、
そこに悪しき現代の風潮も確実に蝕んでいて、
そのアンバランスに住民は翻弄されている面があるのではないでしょうか。
ですから私は広く色々な人、色々な地域と交流することが
絶対に必要だと思うのです。正に私がNPOを立ち上げた趣旨もそこにあります。
地域を出て行く人もいるでしょうから、それに代わる新しい人も
幅広く積極的に迎え入れる。
育った環境や考え方の違う人もいるでしょうが、
積極的に交流することで、それがお互いに適度な緊張感と、
相手への配慮を育むと思います。そしてそれが地域全体に好循環を
もたらすと思います。もちろん現実はこのように単純ではありませんが、
原理はそうだと思うのです。
実は先程の東北の県では数年前から県上げて、
真剣に自殺予防と移住対策に乗り出しています。
そして確実に改善が見られていると聞きます。
汚名を返上する日も近いのではないでしょうか。
冬季オリンピック以後、一部を除いて人口減少と沈滞する経済が続く我が長野県。
あいつが悪い、こいつが悪いと人のせいにしているときは終わりました、
一人一人が自分の出来ることから始めるときだ、
という思いを強くして私はシンポジウムを後にしました。
2007年10月07日
倉本聰氏他「ふるさと回帰フェア」で移住を大いに語る
今年で第三回目となる移住・ふるさと体験等の全国的な一大イベント、
「ふるさと回帰フェア2007」が、全国42道府県240自治体が参加して、
10月5,6日東京の大手町で開催されました。
今年も天候に恵まれ、歩行者天国では恒例となった農産物のプレゼントも有り、
大変な賑わいでした。
(今年はお米1㎏と福島県いわき市提供の焼きサンマを、各先着1000人にプレゼント)


私も昨年に引き続いて参加、見学してきました。
我が長野県からは、長野県庁・田舎暮らし案内人の若林さんと
Iターン相談員の小口さんなどの他、
駒ヶ根市、飯山市、松本市、原村、箕輪町、売木村、上松町も
相談コーナーのブースを出しました。
特に飯山市、原村、売木村はプレゼンテーションも行い、注目されました。
でもこんな良い機会にもかかわらず、長野県関係の参加がとても少ない気がします。
東北や北海道、四国などに勢いを感じました。
記念講演では、「北の国から」などの脚本で知られる、
有名な脚本家、劇作家、演出家の倉本聰さんが、
1977年に北海道の富良野に移住で苦労した裏話などを披露。
その中で「現代の日本人は生きるのに急ぎすぎている、
このままでは大変マズイ、体がついて行かなくなっている、
トランクが先に行っているので、
時々止まって体を待ってあげなければいけないだろう」
と語ったのがとても印象に残りました。
続く
2007年09月02日
移住の課題、仕事が先か住むのが先か?その1

今まで住んでいた所を去って、遠く離れた遠隔地、
特に全く親戚や知り合いもいない所に、移住するという時に必ず直面する、
避けて通れない重要な問題が、仕事の事と住まいの事です。
恥ずかしながら、もう34年も前の事になりますが、
私が初めて東京に出て、学生生活を始めた時の事を思い出すと、
西も東も判らないなかで、学校の推薦する北区滝野川の下宿に、
親に同伴してもらい、そこで親が保証人になって契約をしました。
その後2年位して、少しでも田舎の環境に近い所に移りたくて、
当時はまだ緑の多かった東京の郊外、三鷹に自分でアパートを見つけ、
引っ越しましたが、その時も親に連帯保証人になってもらいました。
その時感じたことは、しばらくそこに住んでみないと、
そこの様子は判らないと言うことです。
仕事も同じではないでしょうか。
またまた私事ですみませんが、親が大学4年の年に退職し、
それから間もなく病院に入院してしまったものですから、
否が応でも卒業して地元で就職せざるを得なくなってしまいました。
そんな訳でろくな就職活動もできなくて、往生した経験があります。
4年程地元の小さな会社にアルバイトのような感じで勤めた後、
現在の会社に勤めたわけですが、その後は転職することなく気がつけば、
25年が経ってしまいました。
そして今思っていることは、自分に合いそうな就職先の情報は、
そこに住んである程度その気になって集めないと入ってこないし、
それでも本当のことは、実際勤めてみないと判らないと言うこと。
PRが上手な会社でそのイメージだけで入社すると、
えらい目に遭うこともある。
宣伝を全くしない、または一般向けの宣伝をあまり必要としない、
BtoBの会社の中にもけっこう優良企業があるし、
自分にとっての良い会社とは、規模でもないし、社歴でもない。
小さくて新しければ恐らく課題山積みですが、
だからこそ自分の関与によって、
その課題をひとつずつ解決してゆくことで、
将来大化けさせる可能性だって大いに有りえます。
まあ吹けば飛んでしまう可能性も高いですが。
逆に大きくて伝統のあるところは、短期的に見れば安定している反面、
全てに亘って形式主義・前例主義的で、
動脈硬化を起こして活力が失われている可能性だってある。
事実老舗の倒産が最近は多いのです。
こんなことは入ってみて、暫くしなければ分かるものではありません。
だから移住には慣らし期間が、絶対に必要だと私は思うのです。
しかしそこにはタイトルに有る通り
「仕事が先か住むのが先か?」
など、なかなか難しい問題がはらんでいます。
すみません、この続きはまた回を改めて述べさせてください。
2007年08月30日
沖縄の人も信州に住みたい!?

当NPO法人が企画・発行して、今年の6月に全国発売したガイドブック
「信州に住もう!2007」ですが、最近共同通信の配信で本の紹介記事が、
全国の地方新聞にぽつぽつ掲載され始めたらしく、
遠隔地から問い合わせを頂く機会が増えました。
特に今日は沖縄の那覇市の方から、「琉球新報の記事で見たが、
この本はどの様にしたら手に入るのか」との電話を頂いて驚きました。
沖縄といったら、信州、北海道と並んで移住希望地の一位を争うところで、
石垣島などはバブルの態をなしているとか。
(そう言えば信州の軽井沢も似たようなものかも)
「沖縄は人気の的で、私も移住したいくらいですよ」と私が言ったら、
その方は「沖縄は熱くて熱くて、以前信州に行ったことがあるけれど、
本当に信州は良いところだ」と言われました。
隣の芝生はよく見えるのかもしれません。
ただこんな事を聞いたことがあります。
新潟在住の農家の主婦の話で、春から秋までは新潟、農作業が終わって翌年の春、
農作業が始まるまでは沖縄暮らしという人が、実際にいるということを。
これを信州に置き換えることも可能でしょうか。
いやもう実行している方がいるかもしれません。
そんな情報があったら、どうぞ教えてください。





